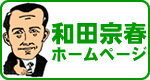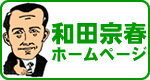2012年7月15日掲載
教育、地方の閉鎖性が問題だ!
―大津市中2自殺事件―
奇妙な事件です。去年10月におきた男子生徒の自殺です。半年以上経って大騒ぎになったきっかけは生徒の父親が警察に「いじめの相談にいっていた」にもかかわらず署員は「事実認定が困難」としたために被害届けを出さなかった。そして、いよいよ警察は捜査に入ったということ。
これほど時間がかかった理由は、教育の世界は完全無欠を装って非を認めない体質があるということです。とくに義務教育は人間形成の基本を教えるはずの場所ですから誤ったこと、不正義が起こるはずがない、という前提で国、県、市、村へと一貫した思想が徹底しています。それだけに学校や組織内の開示はしたくないという心理が働いています。
これは警察にもいえることですが自分たちは国家社会の手本であるという気概が自家中毒を起こす場合もあります。
時間が経ってくるとあれもこれもという事実が明らかになってきました。大津市では市長と教育委員会の見方が相反するようになっています。役人が完璧論を守ろうとするのに選挙で選ばれた市長が現実論で処理しようとする差です。とにかく教育界は秘密主義、閉鎖社会で外見を取り繕うところです。
それだけに社会の一般常識が通じにくい、「先生」といわれることに甘んじている人が多いところです。ましてや地方都市ともなると、まだまだ「先生」の立場は強いものがあって外からの意見、批判に耳を貸すことの少ない職場ではないでしょうか。
―「いじめ」への疑問―
日本の漢字は表意文字です。文字から意味を類推できます。例えばレイプされたというのと、強姦されたというのでは受け止め方が違うと思います。「いじめ」が殺人になったり、自殺に追い込んだりするほど重要な表現にはなっていません。「いじめ」はあくまで軽く相手に心を乱させるような行為をすることでしょう。すぐに了解して仲直りをするいろいろと種類が考えられるものです。ですから「いじめ」という言葉の持っている軽率さとは似合わないものになっているのです。そうなれば執っこい嫌がらせや、身体に触れることは別な用語で明確に犯罪になると規定すべきなのです。小、中学生だから、学校の行き帰りだからという甘えが通じない厳しいしつけが必要なのです。それを越えた時に、例えば「学生犯罪」となることを教えることです。子どもは可愛い、無心だ、罪がないという甘やかしが学校、教師、児童、生徒を別世界にとどめているのです。
このような事件になって大騒ぎをする。そしてまた全国一律に文科省は点検を指示する。時間が経てばまた元に戻る。これを繰り返すのです。小、中学生に社会が求めるものは何か。逆も考えて、その時だけにしない、永遠の教育問題であると考えるべきです。
7月12日 記
|