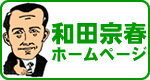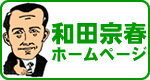3月12日掲載
都立病院に伝統医療を シリーズその4
日本の伝統医療が吉益東洞によって出発したことは前回書きました。また華岡青洲についても触れました。そのような伝統医療を打ち消したのは明治政府の欧化政策だったのです。
19世紀になると天然痘などの流行病の予防法や消毒法による外科的治療技術が進み日本にも入ってきました。これを下地にして、1873年(明治6年)に内務省令の「医術開業試験規則および医師免許規則」が出され、漢方医は医師と認められなくなったのです。これが今日まで漢方が西洋医療と比べて劣勢であった理由なのです。
もとより漢方勢力も帝国議会へ請願をくり返したのですが、相手にされませんでした。そして漢方は一気に衰微していったのです。
この風潮は「舶来ものに弱い」日本の体質を明らかにした例です。
島国で争い事を好まない、すべて受け入れる軟弱な気質に原因があります。
現代日本にも流れている習慣病といえるでしょう。
さて、明治政府に捨てられた漢方はどう再興していったのでしょうか。
大正、昭和になって再び動きが活発になったのです。
昭和2年には中山忠道が『漢方医学の新研究』を出し、漢方の再評価を訴えました。
そして、和田啓十郎、湯本求真、大塚敬節などが復活に貢献したのです。
その後、1960年代になって薬の副作用が国家の問題となり、漢方医療への見方が変わるのです。それも女性にかかわる問題です。
サリドマイドの服用で、手足の発育不全の子どもが生まれる薬害事件です。
1976年には医療用の漢方製剤に健康保険が適用になり、それまで煎じ薬でしたが、その手間がないエキス製剤となり顆粒で袋に入ったものとなったのです。このように漢方再興につくした人々や製剤の顆粒化などで普及されていったのです。
3月10日 記 |