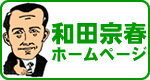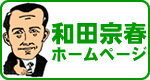3月12日掲載
都立病院に伝統医療を シリーズその3
漢方は中国の療法ではなく日本の伝統医療ということは前に述べました。
十八世紀の中頃に日本ではじめて人体解剖し、図録『蔵志』を出版したのが山脇東洋でしたが、あまり知られていません。有名な杉田玄白、前野良沢の解剖より17年も早かったのです。
山脇東洋の弟子が吉益東洞で彼が漢方の祖といわれる人物です。
この彼に有吉佐和子さんの小説『華岡青洲の妻』で知られる華岡が全身麻酔を世界で初めて成功させたのです。このように進取の心の豊かな日本人がいたのです。このような人々の実績を受けて今日の日本の漢方があります。
現在は90%の医師が漢方を処方するまでに普及してきています。
西洋医学と漢方の融合に気づきはじめたそれぞれの医師は手を取り合って患者のために日本の伝統医療を確立してほしいものです。
たとえばウイルスを叩くという発想や、生体反応として発熱を抑えるという西洋医学の考えに対して、東洋医学では熱は敵ではなく、生体防衛のための味方であると考えるのです。
ウイルスは熱に弱いので、熱とともに体の外に追い出すことができるのです。
3月10日 記 |