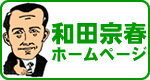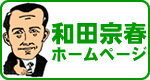3月10日掲載
都立病院に伝統医療を シリーズその2
伝統医療すなわち漢方は古いものと考えがちですが、その効能はインフルエンザにも抗がん剤の副作用を抑えるという面にもあらわれていて、最近注目を集めています。
アトピーや喘息にも良いようです。じんわりと効いてくるのです。
人間の体が暑くても寒くても平常に働かないのと同じに、中庸均衡が病気にならない、なっても回復させる力が漢方にあるといっているのかもしれません。
西洋医学でやるべきことをやった上で、漢方を加えると効果が高い。手術は西洋医学、漢方とうまく組み合わせることで、よりよい医療が成立するのでしょう。
生活態度も漢方は自然を主張します。生活に季節性が薄れてきたことです。
夏のエアコンの冷えすぎ、冬にトマトを食べられることなども体にとっては迷惑なことです。
一年を通して体は冷やされていることになります。
体は冷やすことで、低体温になったりして不調が出てくるようです。
患者にもわがままな人がいます。「酒の飲みすぎ、すぐやめましょう」「チョコレートを我慢しましょう」と指導しても、できません。それで病気治療は無理です。
日常生活にわがままがあって、それが病気を誘発しているのかもしれません。したいことはする、しかし我慢はしないというのでは治るものも治りません。
また病気になることの可能性は高まります。世相は欲求開放の時代です。
自分を自分であらしめるために、いま欲求、欲望を抑えるという制約は大事なことです。しかし、現代の消費の上に成長が成り立っている仕組みは、立ち止まって考える、引き返す、止めることを許そうとはしません。大きな川に浮かべられた一本の小さな木のように私たちを扱います。抵抗する力、それを継続する意志力には相当の覚悟がいります。心では批判しても疲れる批評、行動を避けて迎合してしまいます。一人が十人、十人が一万人となり全国民になったのが現代です。西洋医療がすべてではない、漢方(伝統医療)も活用したいという声が大きくなってくることは、西洋医療万能社会に、抵抗して自分に合った医療、個性的な医療を求める自然な声だと思うのです。それには民間、公共を問わず相談、治療機会を与えるような病院窓口が必要です。そんな病院窓口を私の関わる都立病院にまず設置しましょう。
いまは一つもないのです。
3月10日 記 |